先生として働く中で、ミスやトラブルが起こったとき、
「私が悪いの?」と自分を責めてしまうことはありませんか?
子どもへの指導、保護者対応、同僚との関係…
学校ではさまざまな出来事が起こります。
そして、
責任感が強い先生ほど、
何か問題があったときに
「もっと違う対応ができたのでは?」と考え、
必要以上に自分を責めてしまうことがあります。
でも、
本当にすべて「先生のせい」なのでしょうか?
今回は、
「自分が悪いのかも…」と考えてしまう先生が、
少しでも楽になれるように、
自分を責めすぎないための視点を紹介します。
「私が悪いの?」と考えがちな状況と理由
子どもに対して厳しく叱った後の罪悪感
子どもを厳しく叱った後、
「言いすぎたかもしれない…」
「もう少し穏やかに伝えればよか
と後悔することはありませんか?
でも、先生が本当に悪いのでしょうか?
厳しく叱ることには、理由があったはずです。
子どもにとって必要な指導だった可能性もあります。
感情的に怒鳴るのとは違い、
ルールを守らせるために叱ることは、
決して悪いことではありません。
「叱ること=悪いこと」ではなく、
「子どもにどう伝えるか?」が大切なのです。

保護者対応でクレームを受けたとき
保護者からクレームが来ると、
「自分の対応が悪かったのかも…」
と落ち込むことがあります。
しかし、
保護者の意見がすべて正しいわけではありません。
先生の対応に問題があった場合もありますが、
時には保護者の要求が過剰だったり、
相手の価値観の違いによるものだったりすることもあります。
クレームを受けたときは、
「これは本当に私が悪かったのか?」と
冷静に振り返ることが大切です。
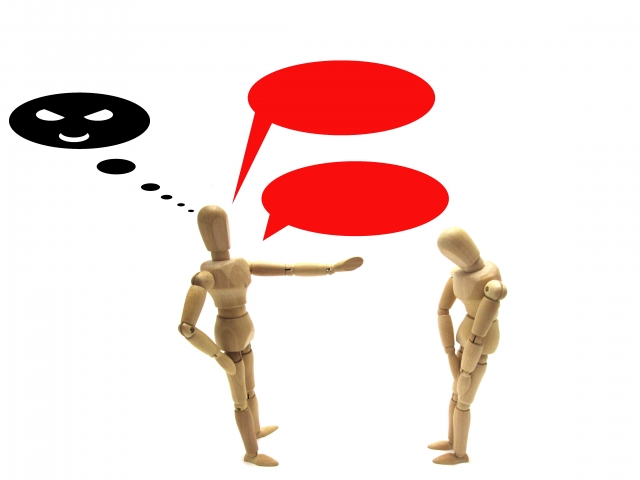
同僚や管理職からの評価が厳しいとき
授業や対応について、
同僚や管理職から厳しい言葉を受けると、
「私のやり方が間違っているのかも…」
と自信をなくしてしまうことがあります。
しかし、指摘を受けたからといって、
必ずしも先生のやり方が間違っているとは限りません。
指導方法にはさまざまな考え方があり、
学校ごとに文化も違います。
「私のやり方が合わないだけかもしれない」と、
一歩引いて考えることも大切です。

自分を責めすぎないための3つの視点
「本当に自分だけの責任か?」と問い直す
問題が起きたとき、
すべてを自分の責任と考えるクセはありませんか?
もちろん、自分に改善できる点はあるかもしれません。
しかし、
「自分にできること」と
「自分のせいではないこと」を
分けて考えることが大切です。
すべてを自分の責任にしてしまうと、
相手の責任まで自分で背負うことになり、
その人自身が学んで成長する機会を奪ってしまうことにも
なりかねません。
・子どもの態度は、家庭環境や成長の過程も影響する
・保護者のクレームは、相手の受け取り方の問題かもしれない
・同僚や管理職の評価は、その人の価値観によるもの
「私が悪い」とすぐに結論を出すのではなく、
「本当にそうなのか?」と考えてみましょう。

「100%完璧」は無理だと知る
先生も人間です。
すべての問題に完璧に対応することは不可能です。
・子ども全員の要望に100%応えることはできない
・すべての保護者に満足してもらうのは難しい
・職場の人間関係も、すべての人と合うわけではない
「できる限りのことをしたなら、それで十分」 と思うことが、
心を守るポイントです。

自分を責めるより、次にどうするかを考える
過去のミスやトラブルを責めても、状況は変わりません。
大切なのは、「次にどうするか?」です。
・「次回は子どもへの伝え方を変えてみよう」
・「保護者対応で冷静に話す工夫をしよう」
・「同僚や管理職の意見を聞きつつ、
自分のスタイルも大切にしよう」
過去にこだわりすぎず、
未来に目を向けることで、
気持ちが少し楽になります。

先生自身の心を守るためにできること
・「すべて自分のせい」と思わない習慣をつける
問題の責任を冷静に分析し、必要以上に背負わないことが大切です。
・「反省と自己否定は違う」と知る
反省は前向きな学びにつながりますが、自己否定は先生の心を傷つけるものです。
・「先生だって助けを求めていい」と思う
1人で抱え込まず、信頼できる人に相談することで、気持ちが軽くなることもあります。
まとめ:「私が悪いの?」と思ったときに試したいこと
① 「本当に自分だけの責任か?」と問い直す
② 「100%完璧」は無理だと知る
③ 「次にどうするか」を考え、前向きに切り替える
すべてを「自分のせい」と思わず、少しずつ気持ちを楽にしていきましょう。
次回は、「『仕事のことで頭がいっぱい…』を手放す方法」についてお届けします。



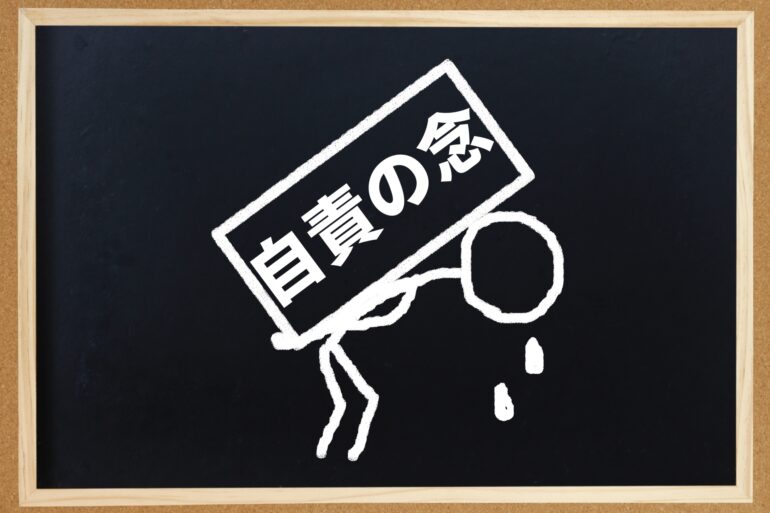


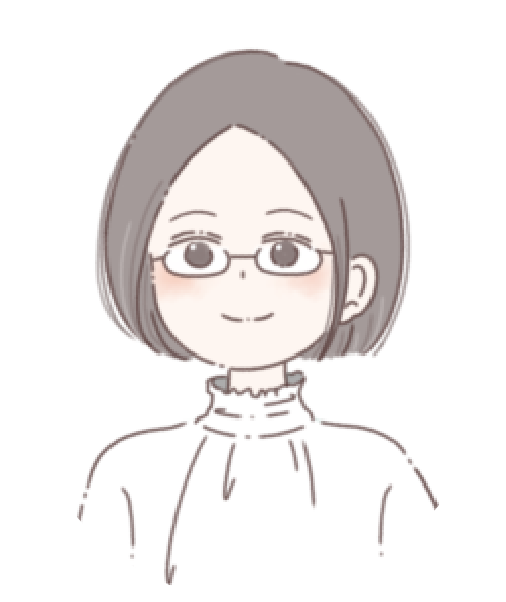


「「私が悪いの?」と自分を責めてしまう先生へvol.79」へのコメント
コメントはありません